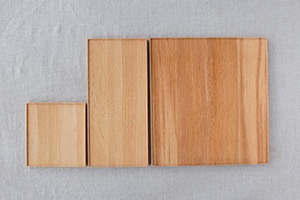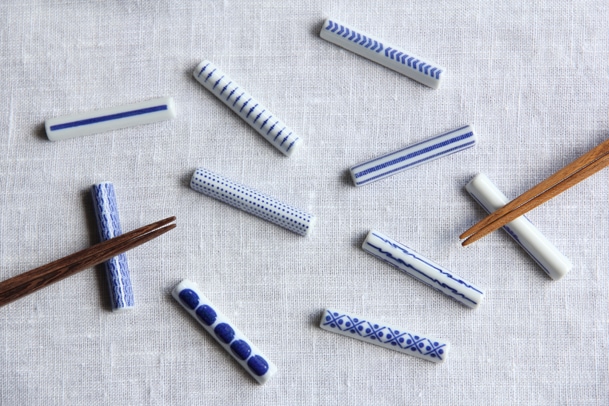カートに追加されました
-
配送について
7月27日(土)朝10時~7月29日(月)朝10時までのご注文は、29日(月)出荷となります。
- 税込1万円以上のご注文で送料無料
- 10時までのご注文で通常即日発送
※受注生産商品除く
-
ギフトラッピングについて
この商品はラッピング可能です
チケットを購入ギフトラッピングは有料で承ります。ラッピングチケットをご購入ください。
飛び鉋 どんぶり (小石原焼)
リズミカルに表面を削る音が聞こえてきそうです。
やわらかい白の化粧土から、茶色の素地が連続的に顔を出すのは、
福岡県で400年以上の歴史を持つ
「小石原焼(こいしわらやき)」の特徴的な技法、「飛び鉋(かんな)」ならではの模様。
サイズは直径16cmほどの「小」と、
18cmほどある「大」の2種類です。
高さはほとんど変わらないので、
高台から縁にかけたカーブの広がりの違いによって、
それぞれの使い方がありそう。
ごはんものだったら「小」。天丼や、海鮮丼も映えそうです。
うどんやラーメン、麺ものは「大」がおすすめ。
厚みがあって、高台もしっかりしているので、
熱い汁物だってへっちゃらです。
もちろん、1人分のご飯だけでなく、
人数分の煮物やサラダをたっぷり盛り合わせても似合うのです。
白地に点、点……と茶色が覗く、至ってシンプルな模様。
手にとって眺めていると、どこかポップな印象も与えます。
だからこそ、和食だけでなく、
日々の食卓でオールマイティに使えるのでしょう。
かわいくなり過ぎず、土くさくなり過ぎず、程よい感じ。
きっとこれからも長く愛される理由の一つに違いありません。
バリエーション&商品詳細
クリックで拡大画像をご覧いただけます。
- 材質
- 陶器
>> お手入れについてはこちら - サイズ
- 小:約φ155×H75~85mm
大:約φ185×H80~90mm - 容量
- 小:約765~805ml(満水)/約612~644ml(8分目)
大:約1155~1195ml(満水)/約924~956ml(8分目)
※容量の計測方法について - 重量
- 小:約360~450g
大:約460~570g - 備考
- ※個体差が大きい商品ですので、サイズ、容量、重量は目安としてお考えください。
直火:× IH:× 電子レンジ:× オーブン:× 食器洗浄機:×
小石原焼(こいしわらやき)について
福岡県朝倉郡東峰村、かつて小石原村と呼ばれたその地域で、
江戸時代から約350年にわたって伝えられている「小石原焼」。
当時の藩主が肥前伊万里より陶工を招き、
中国風の磁器のつくり方を伝えさせたのが始まりと伝えられますが、
その後一時の停滞期を経て、
陶器としてつくられるようになったのは18世紀初頭のこと。
飛び鉋・刷毛目・櫛目・指描き・流し掛け・打ち掛けなどの技法で表現される模様が、
cotogotoでもファンの多い「小鹿田焼(おんたやき)」と共通の特徴です。
それというのも、もともと小石原焼の陶工が、
県境を隔てたお隣の集落である小鹿田に技術を伝授した歴史があるから。
長く伝わるものには、やはり相応の魅力があることを、実感させてくれる器ばかりです。
-
ご購入の前に知っておいていただきたいこと
クリックで拡大画像をご覧いただけます。
- >> 「飛び鉋」という技法によって、表面の模様が施されています。一つ一つ手作業で行っているため、同じ模様は一つとしてありません。 また、鉋の跡が均等でなかったり、薄かったり、重なっていたりする部分も見られます。手仕事ゆえの味わいとしてお楽しみください。
>> 化粧土や釉薬には、にじみ、ムラ、濃淡、凹凸などが見られます。また、貫入(かんにゅう・表面の釉薬に入るひび)も見られますが、ご使用上問題はありません。
>> 大きさや深さには個体差があります。また歪みが見られる場合もあります。
>> 気泡による穴や、小さな土のかたまりがついたまま焼成されてしまったものもございます。
>> 底部分に、がたつきが見られることがあります。
>> ロゴの部分がつぶれている場合があります。
>> 取扱説明書やブランド紹介などは同梱されておりません。予めご了承ください。
>> メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。