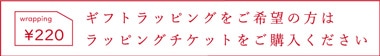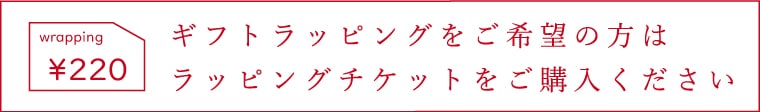木のヘラ (大久保ハウス木工舎)
使いやすさに定評のある「大久保ハウス木工舎」の「木のヘラ」。
「何がそんなに違うの?」と半信半疑で試してみて、納得。
まず、握り方のクセを見抜くかのように、すっと手の中に収まって、
ヘラの先端は腕の延長線上にあるかのような自然さ。
どんな動きも無理なくできるのです。
ブーメランのようなかたちをしていますが、
それが食材を「返す」役目を担ってくれます。
一般的なかたちの木ベラと比べれば、違いは一目瞭然。
炒める食材をフライパンの上で移動させることはできても、
きちんと上下を返すとなると、ここまでスムーズにはいきませんでした。
食材全体に素早く満遍なく火を通すことができるから、時短や美味しさにもつながります。
また、ヘラのカーブがフライパンの緩やかなカーブにぴったり沿って、
食材を取りこぼすこともありません。
さらには、カーブの先端にあるちょっと平らな部分。
これ、別に欠けてしまった訳ではありません。
挽肉を細かくさばくとき、麺をほぐすとき、ここが大活躍するのです。
この飛び抜けた使い心地、そして不思議なかたち。
長野県松本市にて活動されている木工作家・大久保公太郎さんが、
使い手からの声を元にたどり着いたものです。
使い手のニーズに応える例として、左利き用もあるのです。
今まで、無理をして右手用のヘラを使っていた方も、
これからは思う存分、利き手で炒め物ができます。
素材は桜の木。
ツルツルっとした表面の質感に気づくと思います。
それというのも、ヤスリで仕上げるのではなく、
鉋(かんな)だけで削った状態で仕上げているから。
ヤスリがけによる細かな傷がないので、
菌の発生も抑えられて、清潔に長く使えます。
木の道具で不安なお手入れも心配ありません。
使い手の声に応えて、どんどんかたちを変え、進化を続ける大久保さんの道具。
つくり手と使い手が近くでつながっている感覚は、
丁寧につくられた道具だからこそ。
それもきっと、人気の理由の一つに違いありません。
バリエーション&商品詳細
クリックで拡大画像をご覧いただけます。
-
上から「右利き用」と「左利き用」。それぞれの手に合わせて握りやすいようつくられています。
-
裏側の様子。上から「右利き用」と「左利き用」。
-
先端はスパッと切りっぱなしのようなかたちで平らになっています。
-
持ち手は中心が盛り上がり、握りやすいよう厚みがあります。
-
横から見てみると、先端と持ち手の一部が反り、なだらかなカーブを描いていることがわかります。
-
木は桜を使用。自然素材ならではの表情の豊かさが魅力です。また、手で削り出しているため、かたちが少しずつ異なります。一期一会をお楽しみください。
-
左は新しいもの、右はスタッフが1年半ほど愛用しているもの。無塗装なので使い込むほどに色が濃くなり、木が手に馴染んできます。
- 材質
- 桜(無塗装)
>> お手入れについてはこちら - サイズ
- 約W290×D70×H15mm
- 重量
- 約35~40g
- 備考
- 直火:× IH:× 電子レンジ:× オーブン:× 食器洗浄機:×
大久保ハウス木工舎について
ちょっとしなったような独特のかたちの「木のヘラ」や平らな「ジャムスプーン」。
その使い心地にはプロの料理研究家から、日々キッチンに立つ老若男女までが太鼓判を押します。
そんな木の道具をつくるのは、長野県松本市にある木工作家・大久保公太郎さんの「大久保ハウス木工舎」。
もともと松本出身の大久保さん。
ですが、この地に戻って来る前は、 京都で建具職人として働いていたそう。
歴史ある街でものづくりとそれを支える道具と向き合い、 刃物と木工の関係、そしてその歴史をたどるようになったのが、
今の大久保さんの独特の製作スタイルと生みだすもののかたちに繋がっています。
例えば、あえて木を濡らしてから削り始めること。
ヤスリで仕上げるのではなく、鉋で削って表面を仕上げること。
一般的な木工の方法とは真逆に見えるようなことも、 実は木の仕事の歴史をたどったり、
使い手の声を聞きながら試行錯誤を繰り返した末にたどり着いたスタイルです。
従来の在り方を学びながら、とらわれないスタイルによって生み出される道具は、
きっとこれからも多くの愛用者を惹きつけることでしょう。
-
ご購入の前に知っておいていただきたいこと
クリックで拡大画像をご覧いただけます。
- >> 木は自然のものです。一つ一つ木肌の風合いが異なります。木の節があったり、色が均一でない場合もあります。色が濃いものもあれば、薄いものもあります。木の個性ととらえ、一期一会をお楽しみください。
>> 天然の素材を使い、一つ一つ手仕事でつくられているため、サイズやかたちに多少の違いがあります。
>> メーカーの品質基準をクリアしたもののみ販売しております。また、当店でもさらに検品を行った後に、お客様にお届けしております。